
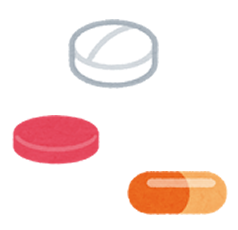 薬局では患者様より、お薬の服用について以下のご質問をいただくことがございます。
薬局では患者様より、お薬の服用について以下のご質問をいただくことがございます。
「薬はなぜ水(もしくはぬるま湯)で飲まないといけないのか?」
「結局飲み込んでしまえばお茶でも同じなんじゃないの?」
「薬だけ飲みこんでもいいんじゃないの?」
実は、薬を水で飲むことには科学的な根拠があるのです。
今回は、その点について解説したいと思います。
まず、内服薬は口の中で唾液や水と混ざり、食道を通って胃に運ばれます。
水を含まずに薬だけを飲み込むと、食道や胃の粘膜に直接触れ、それが刺激になって粘膜に障害(潰瘍や出血)を起こすことがあります。
特にゼラチン製の殻に入ったカプセルは、唾液など少量の水分ではベタベタして、のどや食道に引っかかりやすくなるので注意が必要です。
メーカーは、水と一緒に飲んだ場合を想定して安全性を担保しています。
アルコールは多くの薬の働きに影響を及ぼします。絶対にお酒で薬を飲んではいけません。
特に催眠鎮静薬や抗アレルギー薬と一緒にお酒を飲むと、作用を増強させてしまい、強い眠気や意識障害を引き起こす危険性も考えられます。
このほかに、薬とアルコールの相互作用として、有効成分の血中濃度の上昇による作用・副作用の増強、中枢神経の抑制による呼吸抑制や心停止、アルコールの分解を抑制することによる頭痛、嘔吐(おうと)、顔面紅潮、血管の拡張による起立性低血圧や失神などが挙げられます。
中枢神経を刺激するカフェインも、薬との相性が良くない物質の一つです。
鎮咳去痰薬(せき止め)に配合されているテオフィリンやアミノフィリンは、カフェインと同じ系統の成分であるため、カフェインを多く含む飲み物と一緒に飲むと作用が強く出てしまい、不眠やふるえ、吐き気などを引き起こします(禁忌に相当)。
また、かぜ薬やせき止めに配合されている、麻黄(まおう)やエフェドリンでは作用が強められ、不眠や不整脈、情動障害(気分の落ち込みなど)といった症状が表れることがわかっています。
コーヒーや紅茶などを飲んだ場合、30分以上空けてから薬を飲むようにしてください。
カルシウムやたんぱく質を豊富に含む牛乳は、薬との相互作用を引き起こしやすいので注意が必要です。
抗生物質の中には、有効成分が牛乳中のカルシウムと結合して、効果が半減してしまうものがあります。
また、牛乳はアルカリ性で、胃酸を中和する働きがあります。ところが、胃の中の酸性度が下がると、胃酸から薬を守るためのコーティングが破壊されてしまう薬があります。
特に、腸での効果が期待される便秘薬などは、牛乳で服用すると胃の中で錠剤を覆っているコーティングがはがれてしまい、有効成分が溶け出してしまいます。
 また、グレープフルーツジュースは、薬の代謝酵素の働きを弱める有機化合物(フラノクマリン)を含むため、薬の代謝に時間がかかってしまい、効果を増強させることがわかっています。
また、グレープフルーツジュースは、薬の代謝酵素の働きを弱める有機化合物(フラノクマリン)を含むため、薬の代謝に時間がかかってしまい、効果を増強させることがわかっています。
主に、降圧薬(カルシウム拮抗薬)や抗血小板薬といった、医療機関で処方された薬では注意が必要です。
その他にもスポーツドリンク、ミネラルウォーターなど注意が必要な飲み物があります。
内服薬の注意事項にお薬は水かぬるま湯で飲んでくださいと書かれているものが多いです。
これには様々な理由があるのですね。しかしながら、現在は口腔内崩壊錠(OD錠など)といった水がなくても唾液で飲み込めるお薬もあります。
製薬技術の進歩とともに様々な剤型が増えてきて、服薬という行為ひとつとっても少しずつ便利になってきています。
著者:アイン薬局 四条烏丸店 薬局長 沢田 真史